特集記事(小中学校)
- TOP
- 特集記事(小中学校)
- お悩み解決!Q&A 理解の定着度に差があるときの授…
【今回、回答していただいた先生】
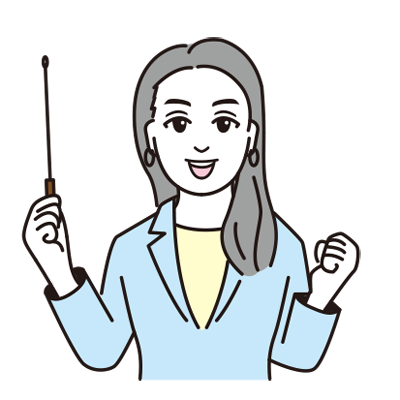
大村 英視 先生
1998年より東京都の公立小学校で教員となり、現在28年目。2025年目黒区立月光原小学校に赴任。算数・数学が専門でない先生方にも、「子どもと一緒に楽しみながら授業をつくる」ことの大切さと可能性を伝えられる教員を目指しています。
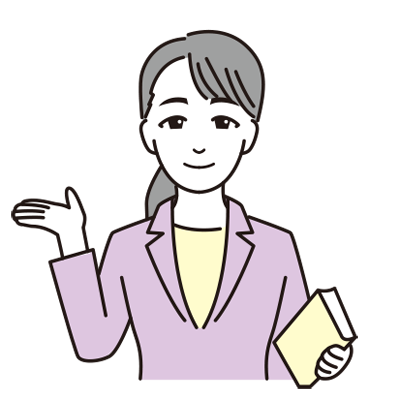
横須賀 咲子 先生
2001年より東京都の公立小学校で教員となり、現在25年目。2021年台東区立浅草小学校に赴任。「子どもたちの声でつくる算数授業」を目指して日々奮闘しています。
Q.
クラスの中で、学習が遅れがちな児童がいます。授業でどのような手だてをすればよいでしょうか。
A.
わからなくて当たり前、というスタンスで授業を進めましょう。
クラスには様々な児童がいますので、理解の定着に差があるのは当然です。学習が遅れがちな児童に配慮しつつ、先生がクラス全体に「わからなくても当たり前、わかるようになったらすごい」というメッセージを出したいですね。
例えば、児童が考えを説明したときに、「今の考え方みんなわかった?先生はわからなかったから、わかった人がもう1回説明してくれる?」というように、先生が「わからない」役を担います。「1回でわからなくても、ゆっくり考えていけばいいんだよ」というスタンスで、より多くの児童が授業に向かう気持ちを高められるようにしたいです。
遅れがちな児童には、机間指導でフォローするようにしていますが、どのくらい机間指導に入ればよいか悩んでいます。
机間指導でのフォローはもちろん大切ですが、いつも特定の児童を机間指導することで、その児童が学習に向かう気持ちを持てなくなってしまう場合もあります。例えば、本時の問題の自力解決のときはクラス全体を机間指導するようにして、まとめの後の適用問題のときにのみ遅れがちな児童のフォローに入るなど、指導のタイミングやその児童の気持ちも読み取りながら、机間指導するようにしましょう。
児童どうしに委ねると、自分に合った学び方を選べる児童もいます。
クラスの中で教え合う時間をつくってみても、よいでしょう。「わからない人は、誰に聞いてもいいよ」と伝えると、児童は自分に合った教え方をしてくれる相手を見つけます。先生に教えてほしい児童は先生に聞きに行く、考え方を詳しく知りたい児童はそういう説明をしてくれる児童に聞きに行く、答えの出し方をストレートに知りたい児童は…というように、分かれていきます。先生も、「あの子は、こういう学び方が好きなんだな」ということが分かるので、次の指導へのヒントになると思います。
その他のコンテンツ

