特集記事(小中学校)
- TOP
- 特集記事(小中学校)
- お悩み解決!Q&A 数学的な見方・考え方を働かせる…
【今回、回答していただいた先生】
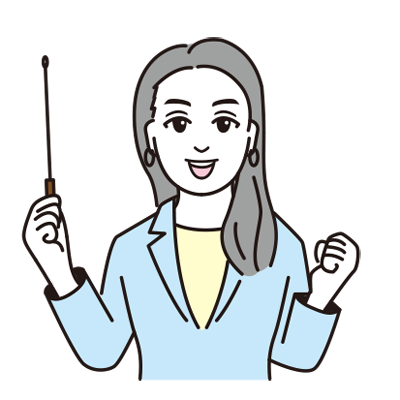
大村 英視 先生
1998年より東京都の公立小学校で教員となり、現在28年目。2025年目黒区立月光原小学校に赴任。算数・数学が専門でない先生方にも、「子どもと一緒に楽しみながら授業をつくる」ことの大切さと可能性を伝えられる教員を目指しています。
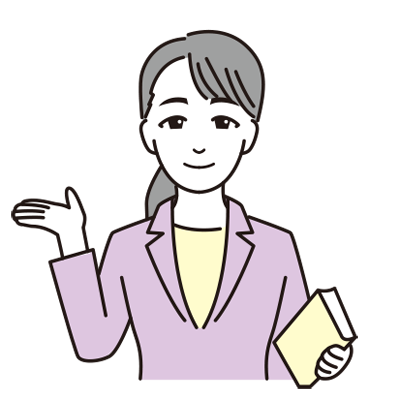
横須賀 咲子 先生
2001年より東京都の公立小学校で教員となり、現在25年目。2021年台東区立浅草小学校に赴任。「子どもたちの声でつくる算数授業」を目指して日々奮闘しています。
Q.
数学的な見方・考え方を働かせて考える大切さを、児童に実感させたいと考えています。どのような工夫がありますか。
A.
児童の考えから、数学的な見方・考え方をキャッチする力をつけましょう。
「数学的な見方・考え方」というと難しく聞こえるかもしれませんが、実は児童は自然と見方・考え方を働かせています。先生は、単元の学習に入る前に教材研究をして、「こういう見方・考え方が出てきたら、キャッチしよう」と意識しておくとよいと思います。
授業では、児童の考えの中にある見方・考え方を見過ごさないでキャッチして、「算数として大事だね」「前の学習が使えたね」などと価値づけるとよいでしょう。板書でも強調しておくと、児童に意識づけることができると思います。
単元の中にある数学的な見方・考え方を、児童が全部完璧に働かせていなくてもいいと思います。とくに重要な見方・考え方だけでも、働かせている瞬間を見過ごさずキャッチしてあげましょう。
数学的な見方・考え方に着目した教材研究は、どう進めればいいですか。
事前に教科書を読み込むことから、始めてみてはいかがでしょうか。
教科書にある子どもの吹き出しには、見方・考え方が表現されています。実際の授業で、自分のクラスの児童はその見方・考え方をどう表現するのか、いくつかのパターンを想定しておくとよいでしょう。教科書通りの整った表現ではなくても、ほんの一部でも、崩れた表現でも、児童なりの表現で見方・考え方を説明している姿をとらえて、授業で取り上げていってください。
知識・技能が定着していない児童は、数学的な見方・考え方を働かせることは難しいですか。
知識・技能は先生が補いつつ、既習を活用しようとする姿勢を引き出すようにしましょう。
たとえば5年の小数のかけ算で、\(80×2.3\)の計算のしかたを考えるときに、「2.3は中途半端な数だから計算できない」「2や3のように、きちんとした数ならできる」というような考えが出されます。この児童は、「整数」という用語の知識は定着していないかもしれませんが、整数であれば既習を活用して計算できるという思いは持っています。先生はその思いをキャッチして、「整数なら計算できそうなんだね。整数にするには、どうすればいいのかな。」というように、知識は補いつつ、児童が考える余地を残す発問を意識することが大切です。
数学的な見方・考え方を働かせていない算数の授業はないと思います。児童のことばをキャッチできるように、先生がしっかりと準備をして授業に臨みたいですね。
その他のコンテンツ

