特集記事(小中学校)
- TOP
- 特集記事(小中学校)
- お悩み解決!Q&A 主体的・対話的で深い学びを実現…
【今回、回答していただいた先生】
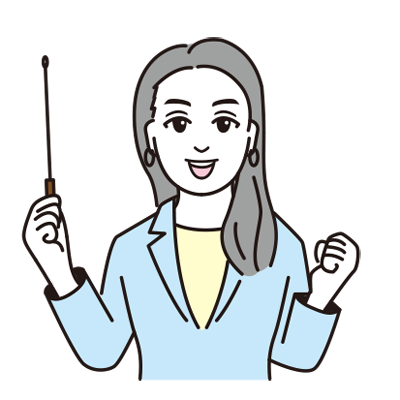
大村 英視 先生
1998年より東京都の公立小学校で教員となり、現在28年目。2025年目黒区立月光原小学校に赴任。算数・数学が専門でない先生方にも、「子どもと一緒に楽しみながら授業をつくる」ことの大切さと可能性を伝えられる教員を目指しています。
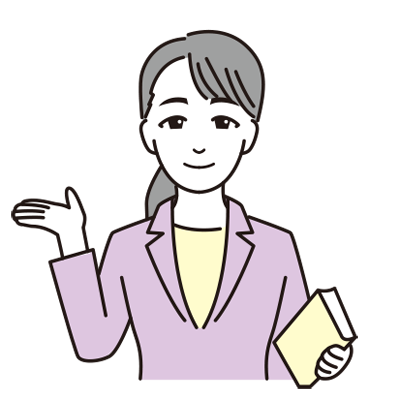
横須賀 咲子 先生
2001年より東京都の公立小学校で教員となり、現在25年目。2021年台東区立浅草小学校に赴任。「子どもたちの声でつくる算数授業」を目指して日々奮闘しています。
Q.
主体的・対話的で深い学びの実現について、「主体的」「対話的」ということは分かっていてはいるが、どうしても解き方や方法を教え込む授業スタイルになってしまうことに悩んでいます。
A.
教師が「教えすぎない」勇気を持ちましょう。
教師が一方的に話し続ける授業では、子どもは受け身になってしまい、主体性は育ちにくいかと思います。そのため、教師は解説者ではなく、子どもたちの思考を促すファシリテーターに徹します。
また、「早くやり方を教えてほしい」という子どもの声があっても、ぐっとこらえてヒントを与えながら、子どもたち自身に考えさせ、対話させる時間を辛抱強く設けることが重要です。これにより、子どもに「学習は自分たちが主役だ」という意識が芽生えます。
「教え込み」を避けるための「次の一手」を準備しましょう。
子どもの思考を止めずに学びを促すため、教師は答えを教える以外の具体的な「次の一手」を教材研究の段階で複数用意しておくことが重要です。
例えば、「この解き方は絶対に自分からは言わない」といった「言わない言葉」を決めておくのはいかがでしょうか。また、すぐに教えるのではなく、「何に困っているの?」というような児童の思考を促すような問いかけを行い、対話のきっかけをつくります。
さらに、教科書の解答例をすべて見せるのではなく、まずは「式だけ」「図だけ」を提示し、「どういうふうに考えたんだと思う?」と問いかけ、子どもどうしで考えさせるようにすることもあります。
子どもたちに考えさせる時間を設けたいと思っているのですが、時間がかかってしまい授業の進度に影響が出てしまうことが不安です。
「時間内にすべてを終える」という固定観念を捨ててみましょう。
授業の目的を「教科書の内容を時間内にすべて終わらせる」から、「子どもたちが核心的な内容を深く理解すること」に切り替えます。教科書に書かれている内容をすべて同じ重みで扱うのではなく、授業内で「絶対にやるべきこと」と「時間があればやること」、「宿題で対応すること」などと区別してみてはいかがでしょうか。教師が単元で最も重要な内容を見極め、そこには時間をかけてじっくり取り組むようにします。既習を活用するなど、教材を捉えなおして学習内容に強弱を付けることで「深い学び」にもつながると思います。
教師の「焦り」を減らすためのくふうを事前に備えておきましょう。
時間がかかることで、授業の進度などに対して焦りが生まれることが教え込みになってしまう大きな要因ではないでしょうか。これらを軽減する仕組みや準備を事前にしておくことで子どもたちに考えさせる時間を設けることができると思います。
例えば、教材研究の時点で「きっと子どもはここで手が止まるだろう」「ここはつまずく子が多いだろう」とあらかじめ想定しておくことで授業内で焦らずに対応することにつながります。また、同じ学年担当の教師たちの中で、「最低限ここまで理解できていればOK」という共通理解を作っておくことも考えられます。そうして教師自身が心にゆとりを持つことで、子どもたちが考えたり、話し合ったりする時間を待つことができるようになります。
子どもたちの沈黙する時間が続くことも不安になって教えてしまうことがあります。
「子どもの沈黙」を恐れず、思考の「待ち時間」と捉えてみましょう。
子どもの手が止まり、教室が静かになる「沈黙の時間」は確かに不安になることがあるかもしれませんが、子どもは考えていないのではなく、「自分で考えている時間」と捉え直します。教師が、子どもの沈黙を不安に感じ、焦ってすぐに解説して(教え込んで)しまうのではなく、沈黙は子どもが思考を深めている証拠であると信じ、教師が待つ姿勢を持つことが子どもの主体性を育む第一歩になるのではないでしょうか。
その他のコンテンツ

