今日の授業のひと工夫(小中学校)
- TOP
- 今日の授業のひと工夫(小中学校)
- 【3年8章】標本誤差

統計にはエラーがつきものです。標本調査のエラーには、標本誤差と非標本誤差という2つのエラーがあります。
まず、標本誤差ですが、無作為抽出による推定の結果は、ほとんどの場合、母集団すべてを調べた結果とは一致しません。これは、調査対象を無作為に抽出する際に、どの対象が選ばれるかは偶然的なバラつきによるものなので、誤差が発生します。つまり、少数の標本が母集団の母数(平均や分散)を言いあてることに失敗するというエラーです。
次に、非標本誤差には、次のようなものがあります。
測定誤差、数値の入力ミス、計算ミス、データの紛失、分析のやり方の誤り、質問用紙上の誤解を生む恐れのある不適切な設問、不完全な定義、聞き取り相手側の問題(無知、嘘つき、しゃべりすぎ、記憶まちがいなど)などです。
標本誤差は、どのくらいの確率でどのくらいの誤差になるか、計算をすることができます。どの程度発生しているのかを数字で表すことができるので、それを踏まえた上で考察し、判断することができます。つまり、標本調査を行うときは、標本誤差がどのくらいであるか予測したうえで標本の大きさを決める必要があります。また、調査結果を見る際にも、標本誤差の存在を知っておく必要があります。一方、非標本誤差は、その性質から理論的に扱うことは難しく、誤差の大きさを判断することができません。
教科書p.217のトマトの糖度の調査のように、実際に標本調査を行うときには2つの誤差を意識したいところです。
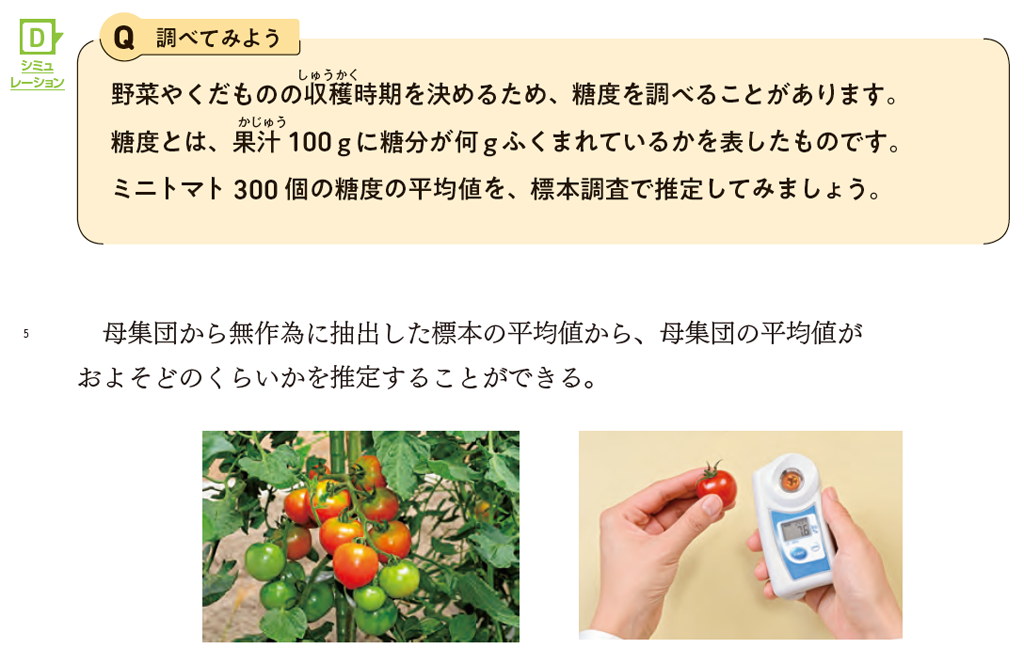
その他のコンテンツ
