特集記事(小中学校)
- TOP
- 特集記事(小中学校)
- 【math connect】トークセッション:生徒…
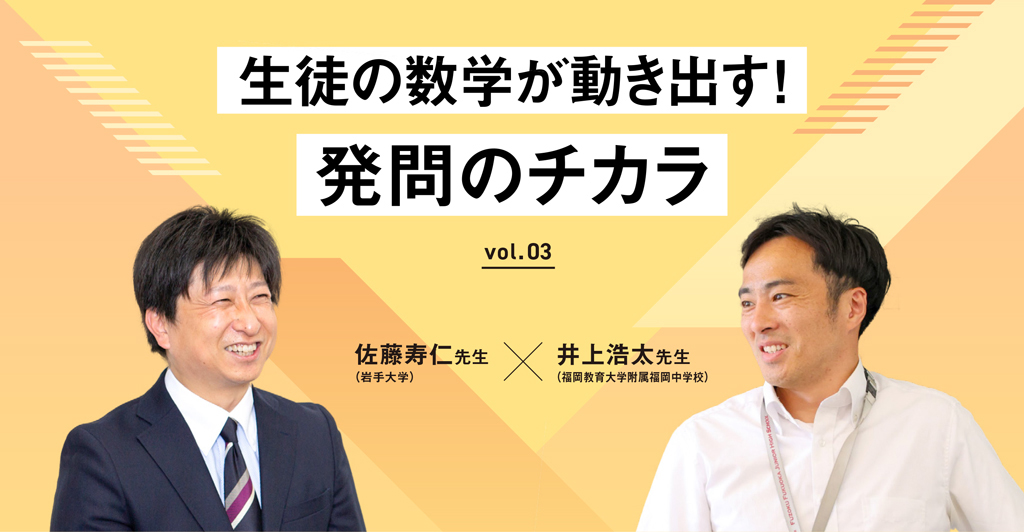
発問と教師の伴走
― 国のほうの動きでいうと、ハイブリッドな教科書も話題になってますが、井上先生、子どもたちがデジタル教科書を使ってみた反応はどうですか?
井上浩太:去年、大学がデジタル教科書の研究を受けてて、私が年3回公開授業をさせてもらいました。デジタル教科書が有効だったという生徒もいましたが、有効でなかったとかいう意見もありました。有効だったところはやっぱり動きが見える点はよい。例えば、円錐の表面積のところで円錐を組み立てたり分解したりを繰り返し自由にできる点がデジタル教科書のいいところなので、自分のタイミングで開いてみたり組み立ててみたりしていました。本質的なところで長さが等しいところが、捉えることができていた印象を受けました。ただ、この生徒たちは、知識として当然知ってるだろうなと思ってたんです。だけど、それをアニメーションとして視覚的に見ることは、かなり有効だったみたいです。
佐藤寿仁:すごいですね。最近、研究の一環で複数の教科書会社のデジタル教科書を見る機会があります。先生の中に「学習者用デジタル教科書を渡してしまうと、先生の出番がなくなってしまう」という人がいます。先生がやっぱりこう数学的な見方・考え方を促すような発問があって考えることだっていっぱいあるし、問い返すことだってたくさんありますよね。先生方はデジタルの動画やアニメーションを視ることで、それだけで子どもは学習内容を理解してしまうのではないかと誤解されていることがあります。
― 中学校は教科書会社に限らず、いろいろな会社が基本的な知識や技能の解説動画を出しています。そういうものを見て、先生の出番がなくなるという話が出てきていると感じています。
佐藤寿仁:ある大学の先生がおっしゃっていたのですけど、昨今の教育が「痒いなっていうところに、掻いてあげている教育」になってしまっていないかということです。それは少し危険だと思います。紙であろうとデジタルであろうと、やっぱり先生の役割はあると思っています。いま、「伴走」という言葉をよく使うじゃないですか。
井上浩太:そうですね。
佐藤寿仁:子どもに「伴走」するってことは「痒い所を掻いてあげる教育」ではないですよね。でも、これまでの教育で教師が重視してこなかったので、とても難しいことなのですよね。今までティーチング(教える)してきましたから、難しさが結構あるのではないですかね。井上先生はどうですか。
井上浩太:自分は伴走っていうのがあんまりイメージが持てていなくて、生徒の思考の流れを意識して授業づくりをするなかで、伴走っていうのが隣でいいのか、1歩前なのか、その辺のイメージは難しいと感じています。
佐藤寿仁:そういう難しさはありますよ。「教師の伴走」が大事ですよと助言したときに、先生たちが「本当に大事ですね。分かりました」って言って、次の授業では、伴走とは言えない並走のような授業をしていました。伴走するためには発問での教師の関わりが大切なんですよね。
井上浩太:そうですね。並走とは違いますもんね。
佐藤寿仁:子どもとのやり取りが入るのはそこですよね。でも並走している授業をよく見ます。生徒と交わらず、子どもが止まったら止まるだけで促すという対応をしていないのですね。
― 今までティーチングが行きすぎて、その反動もあって伴走するという考えが出ていると思うんですけど、その反動が大き過ぎたため、佐藤先生がおっしゃるように並走のような指導になっている部分もあるんでしょうか。子どもたちが主体的に考えられるようにどんな促し方が伴走になるんですかね。
佐藤寿仁:今日のテーマである発問に関していえば、何かの数学的な見方や考え方を促す発問は、直接的になるのだと思います。条件を変えて何かを見出す場面では、「何かを変えて考えてみたらどうとか」という発問ができる思います。でも、この発問は生徒にとって難しいこと言ってますよね。「条件を変えて考えてごらん」、「発展的に考えてごらん」のような発問は直接的に聞くことだって必要だと思います。それをしないで「考えてごらん」だけですと、子どもたちは考えにくいのではないでしょうか。例えば、「まずいいから考えてごらん」と教師が問いかけたことに対して、生徒が本当に自由に考え、「…と考えました」と発言し、すると教師が「いやそうじゃなくて…」といってしまうような場面をみます。それなら、最初から明確に問うたほうが良いですよね。
他の数学的な考え方を促すような場面、例えば類推することもそうですよね。何か分かっていることに対して「同じように考えて」として、類推を促す発問ってありますよね。それも同じように考えています。「類推すること」を分からずして発問すると、生徒は何を考えればよいのかが分からなくなります。だから、数学的な考え方を促す発問ってのはある意味直球の時もあるのですよ。それをぼやかして問うとよくわからなくなってしまうのですよ。
井上浩太:数学的な考え方を促す発問が、直接的な発問でもいいっていうのは非常に勇気づけられました。これまで、発問は間接的にやるべきと教わってきたので、数学的な考え方を促す発問に関しては直接的でもいいというのは、自分としては目から鱗だと感じました。発問について、少し整理がつきそうだなと感じました。
佐藤寿仁:道徳の授業には主発問が存在するじゃないですか。その時間を決定づけるような主たる発問って結構はっきりと伝えますよね。
井上浩太:そうですね。
佐藤寿仁:私はそれに近いと考えています。明確に生徒に問うときというのは、数学の本質に迫る時なんです。そこに躊躇してしまうと学びが浅くなってしまうのですよ。そのような授業が増えつつあるのかなと思っています。それでは学びは前進しないと感じています。
― はっきりと伝えないことが良くない側面もあるんだっていうことを、先生方に伝えていけると、授業がよりよく変わってくのかなと思いました。
井上浩太:はい。
佐藤寿仁:そうですね。伴走すると言いましたが、例えば、「分かってることを生かして、同じように考えることはできませんか?」っていうこの1つの発問が、いわゆる教師の一方的で高い目線から発している発問なのか、一緒に授業の中で子どもと共に歩むような目線なの発問なのかで、受け取り方は全然違うと思うんですよ。教師としての目線で位置で「いいか!みんな、よく聞きなさい」のような感じで、発問してしまうと子どもたちは変に構えてしますよね。でも、一緒に子どもと考えていく中で、まるで自分も生徒と一緒に問題解決して考えてる1人として、そういう発問すれば、生徒の受け止め方が違うのではないかと思います。伴走ってそういうことだと思ってます。
井上浩太:そうですね。
― 授業のなかでは子どもの横にいるように立ち振る舞うことですね。
佐藤寿仁:そうですね。子どもと一緒に問題解決をすることを楽しんで欲しいんですよ。もちろん先生は数学を分かっているけれど…、答えも知ってるし、方法も知っている。だけど、子どもと一緒に問題解決者のひとりとしてね、子どもと一緒に楽しむことができるというのが、数学の授業の楽しさなのではと感じています。どこか先生たちがね「こう教えないと」とかね、「最後に自分が教えないと」という意識があるのですかね。
教科書もそうですよね。問題解決を「ゆうまさん」、「あおいさん」、「ルーローさん」と一緒に歩んでいるのですよね。そこに一緒に子どもも入るし、先生も一緒になって問題解決していく姿勢をみせることはとても大事なんじゃないかなっていつも思うんですね。
井上浩太:そうですね。
― 井上先生、附属中の他教科では自由進度学習を実践されている教科もあるんですよね。
井上浩太:そうですね。自由進度学習を実践している教科もあります。自由進度の良い点や悪い点はありますが、実践されている先生はわからない生徒に個別に対応していけるのでそれはそれでよいと感じているように思います。
佐藤寿仁:教科特性に押し込むつもりはないんですけど、算数・数学は体系的に概念を積み上げていくことが多いので、進み方が自由といわれると何か苦しいものがありますね。他の教科を深く理解しているわけではないのですが、例えば、公民で自由進度学習を行うとなったときに、何かの大きいテーマがあって、自分で調べながら解決し、最後に共有することはあるかもしれないし、それには順序のようなものがあまり関係ないのかなと思います。
井上浩太:そうですね。
佐藤寿仁:算数数学では概念を拡げていくこともあり、その途中がやっぱり大事になってきますよね。平方根における計算の決まりの学習において「加法から取り組んでも乗法から取り組んでもいいよ」というのは少し違和感を感じます。教科書は体系的に構成されていますから。
― 平方根は、掲載内容の順序を1つ動かすのがものすごく難しい章なんです。前後1個入れ替えると、全体の筋が通らなくなってしまうんです。
井上浩太:はい。
― 平方根に限らず、そういったやりにくいところが数学にはいっぱいあるんでしょうね。
佐藤寿仁:おそらくそうですよね。学生がレポートを出してくる時に「数学は体系的に学ぶことが大事」のようなことを書いたレポートがあります。それを読むと、学生は素直に教科書をよみ、そのような意図でよく解釈している感じがしましたね。偏った学び方を優先させると、違和感のある指導になってしまうのはあります。
国のほうでも、ビッグアイデアという話が出てきた時に、何を追い求めていくのか。遠い進路の中で何を求めるものなのか、近い進路の中で何を求めてるものか、教科内で何を求めてるのかね。そういうところをすごく強調し始めたので、そうやって指導を整理するつもりなんだなと見ています。それと学び方のこの噛み合わせですよね。
井上先生、公開研究会はどんな授業を予定しているのですか。
井上浩太:今回6月の研究会は数学科で1本で、授業者は私ではなく自分は研究論の方を担当しています。発問を工夫していけば、生徒が見方・考え方を働かせて、新たな数学をつくっていくだろうという仮説で研究を進めています。授業では学校のグラウンドがちょうど正方形なので、それを利用しようとしています。
佐藤寿仁:正方形のグラウンド、珍しいですね。
井上浩太:正方形のグラウンドにトラックを作るときに、最大でどれぐらいのトラックが作れるだろうかっていう問題から入ろうとしています。円のときに最大になるという話から、平方根を利用して、正方形の対角線を利用するところに焦点化する流れです。
佐藤寿仁:日常事象へ利用する内容ですね。数学は便利なものと言うのは簡単ですが、そのことを実感を伴って感じることが大事ですよね。
井上浩太:あとは、発問ですね。何を狙って、どう発問するかを整理しながら、何パターンか考えています。その授業での生徒の思考がどっちに向かうのかが分からないので、パターンごとの発問を同僚の先生と2人で作ってるとこですね。
佐藤寿仁:指示と発問を分けている先生の授業をみたことがあります。でも、ずっと指示しているような授業に見えました。指示と発問の違いって何かなとか、そういうことも先生たちには考えて欲しいなと思います。また、その数学的な見方・考え方の発動を促すような発問をしてほしいなと思いますね。
Profile
佐藤 寿仁 Toshihito Sato
岩手県公立中学校で11年、岩手大学教育学部附属中学校で6年教職を務め、岩手県岩泉町教育委員会指導主事、国立教育政策研究所学力調査官・教育課程調査官を経て、令和3年度より岩手大学教育学部准教授。
井上 浩太 Kouta Inoue
公立中学校勤務9年、令和元年度福岡教育大学附属福岡中学校にて長期派遣研修、令和5年度より福岡教育大学附属福岡中学校にて専任教諭です。
数学的な見方・考え方を細かく捉え直しています。
東京書籍では、先生方の困り事を募集しています。
日々の校務のなかのさまざまな困り事を、教科書に携わっている経験豊富な先生から解決のアドバイスやヒントをいただいてみませんか。
困り事は、こちらのGoogleフォームからお送りください。
(すべての困り事に対して、回答できかねますことをご了承ください。)
その他のコンテンツ
